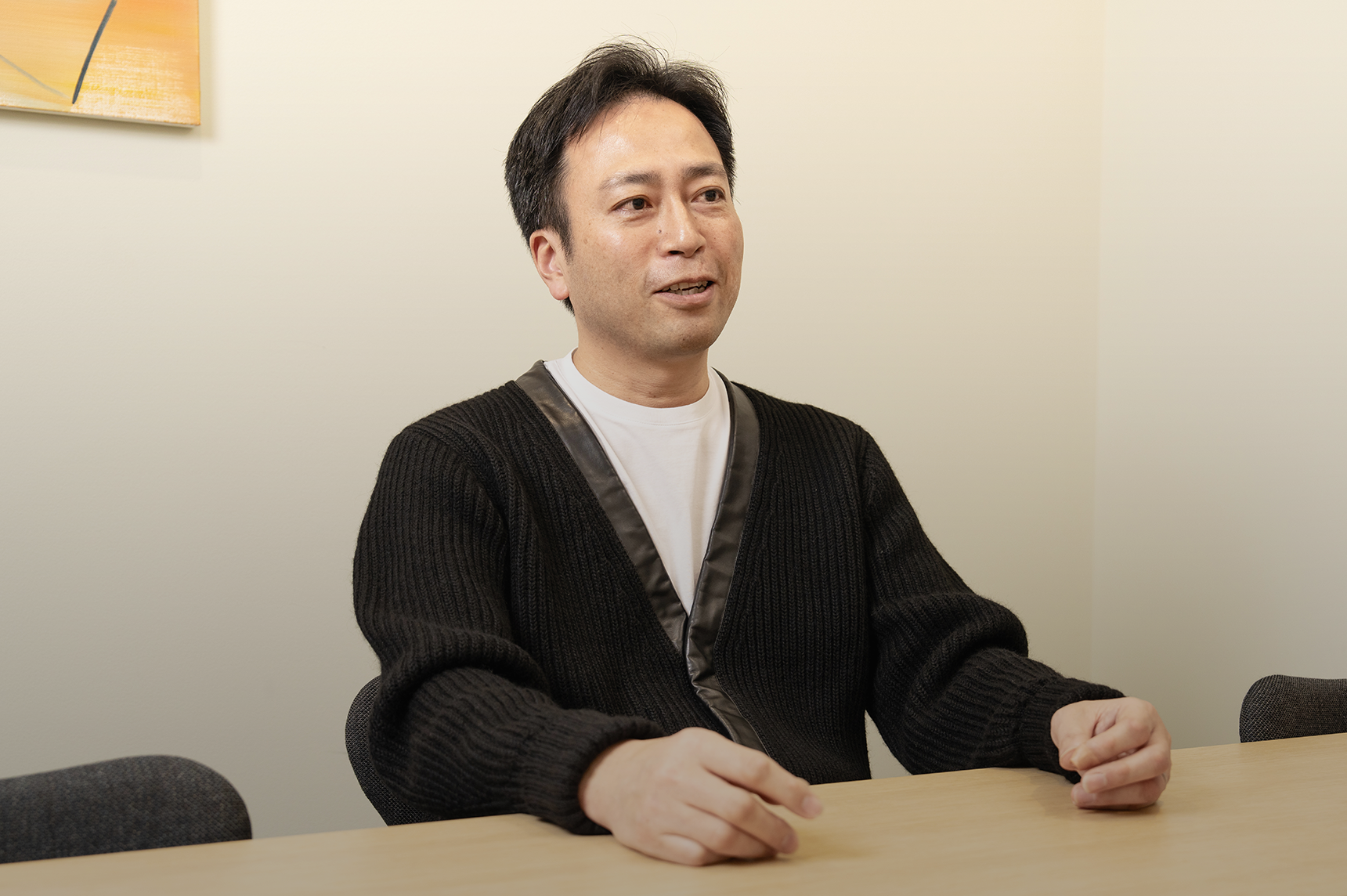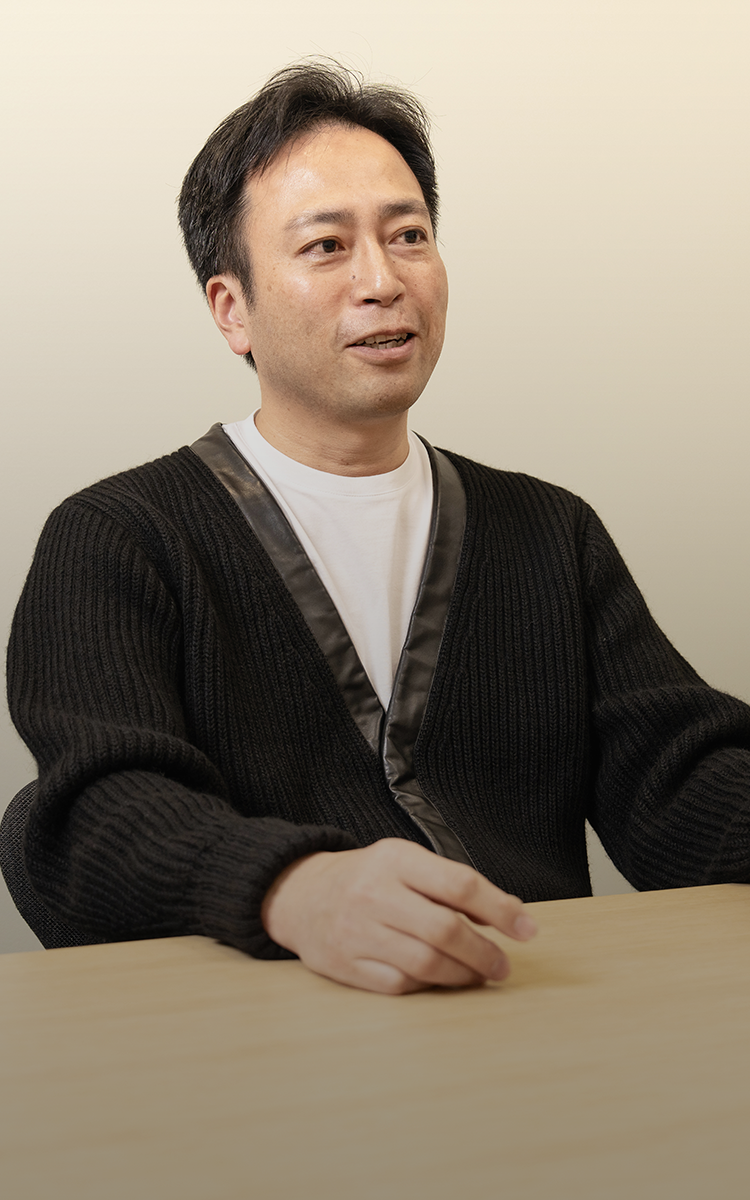Interview
自分がユーザーになれる領域で、知財の経験を生かす
大学時代、知的財産(以下、知財)ゼミに所属して特許や意匠について学んでいた私は、「世界初のものを生み出した企業で知財業務に携わりたい」という思いで就職活動をしていました。
知財には大きく分けて、会社名やサービス名などを保護する「商標」、技術を保護する「特許」、デザインを保護する「意匠」があります。世界初のものを生み出すような企業は知的財産権を重視する傾向があり、そうした現場に自分も関わりたいと考えていたんです。
実際に、船舶用機器の分野において高い技術力を持ち、世界初の製品を生み出した企業に新卒入社し、技術的な知識を身につけながら知財についての理解を深めることができました。一方で、特定のユーザー向けの製品を開発する企業だったこともあり、経験を積むにつれ、「自分がユーザーの立場になれない」ことに問題意識を持つようになりました。
知財の仕事にはユーザー視点が欠かせません。ユーザーがどんな機能を望み、どんな使い方をしたいと思っているかを理解できないと、事業部門へ良い提案ができないからです。
「自分がユーザーになれるものとは?」と模索した結果、幅広くゲーム開発を行う大手エンターテインメント企業へ転職することにしました。ゲームは、自分がユーザーになることもできますし、さらに、ゲーム業界は知財を重要視していたことも理由となりました。
「自分がユーザーになれる商品やサービスに関わる」。この軸は今も大切にしていますね。
その後は長くエンタメ業界に身を置き、次は「人々の生活の根幹を支える“衣食住”の仕事に携わりたい」と考えるようになりました。
当時の私は、衣食住の分野ではテクノロジーの活用が進んでおらず、ゲーム業界と比べて特許に力を入れている企業が少ないように感じていました。その一方で、これからテクノロジーの活用が不可欠になるとも感じていました。そういった分野であれば、知財の仕事で培った経験を生かし、新しい挑戦ができるのではないかと考えたのです。
衣食住の「衣」を支え、新たなサービスや技術を生み出し続けるZOZOに関心が向いたのは、私にとって自然な流れでした。

知財を保護・活用し、一緒に事業を成長させていく
私がディレクターを務める知的財産部は、入社当初の2020年1月に、法務部門にいた仲間とともに3人で立ち上げた部署です。
組織強化を続けて現在は9名ほどの部署となりましたが、実は、それまでZOZOには知財部門がありませんでした。事業部門が個々に知財の保護に取り組んでいましたが、全社を横断して戦略的に知財を考える部署はなかったのです。「それなら自分が一から立ち上げればいい」とワクワクしたことを覚えています。
入社2か月後に知的財産部の設立が決まり、さらにその1か月後には部署の立ち上げに至りました。ZOZOではこうした意思決定や実行がとてもスピーディー。外から入ってきた私が新しい部門をつくることになっても、部署を超えた協力を得られました。
こうして新たに船出した知的財産部は、たくさんの課題と向き合うことになりました。社内でいろいろなスタッフと会話してみたところ、知財の捉え方が想像以上にバラバラだったのです。
全社で統一的な考え方がなく、知財に関わる際には中途入社の人が前職の考え方をもとに進めることが多い状況でした。「ZOZOにとっての知財とは」を明確に示すことが大切だと感じましたね。
事業部門からすると、「知財って、なんとなく面倒」という印象を持ったかもしれません。専門部署が立ち上がったことで、従来は当たり前にやっていたことにも制限がかかるようになったからです。私たちの立場では「これをやってしまうと危ないですよ」と、ブレーキをかけるコミュニケーションも時には必要です。
しかし私は、ただ単に守りに走るような自事(※)はしたくないと強く思っていました。知的財産部が存在する意味は、知財を通じて一緒に事業を成長させていくことにある。そのスタンスを伝え、事業部門が知財を自分ごと化できるよう、根気強くコミュニケーションを重ねてきました。
(※)ZOZOでは、仕事のことを「仕事(仕えること)」ではなく「自事(自然なこと)」であるという意味を込めて、「自事」と表記します。
新サービス保護のため、ZOZO初の「内装の意匠権」取得に挑戦
知的財産部では、各事業部門とのコミュニケーションを通じて、知財を保護・活用したり、知財に関するリスクを低減したりするための戦略立案と実行を担っています。
2022年には、超パーソナルスタイリング体験施設「niaulab by ZOZO」(似合うラボ)という実店舗でのサービスに関わりました。似合うラボは「試着室に飛び込む」という内装コンセプトの施設で、ZOZOのAIとプロのスタイリストが、お客様の「似合う」を見つけるという斬新なサービスです。
この『niaulab』『似合うラボ』というサービス名や、コンセプトである『超パーソナルスタイリングサービス』『Hello, new me.』、「似合う」が分かる動画コンテンツである『niaulab TV』などを商標権で保護。また、サービスにおいてはAIも活用しており、こうした技術については特許権で保護しています。
一方で、「似合うラボ」はスタイリストを中心とした「人」が提供するサービスのため、サービス内容について特許権を取得して保護することが難しい。
こうした実情を踏まえ、私たちが出した結論は、「試着室に飛び込む」という内装コンセプトを「内装の意匠」として保護することでした。
内装の意匠権を取るのはZOZOとしても初の試みでしたが、知的財産部内でさまざまな議論をくり返し、事業部門のこだわりを聞かせてもらいながら、似合うラボのコンセプトに則した保護の形を実現できたと考えています。

バランス感覚で、世界中をカッコよく、世界中に笑顔を。
私自身が知財の業務において大切にしているのは「バランス感覚」です。
事業ポートフォリオを拡大していく中で、いつかは他社の知的財産権と競合するようなケースが出てくるかもしれません。競合他社に対して優位性を保つためにも、彼らが進めている知財戦略や、ビジネスの行方を分析しながら、当社も知財のポートフォリオを強化することが大切です。
とはいえ、予算や人的リソースには限界があります。当社が知的財産権として権利化する場合も、第三者の知的財産権について調査する際にも、ビジネスの規模に応じて、どれだけのコストをかけるべきかを冷静に判断しなければいけません。
当社のどんな事業で、どのような範囲の権利を取得するべきなのか。その戦略を立てる際にもバランス感覚を大切にしています。
社内外の新しい情報を常に収集し、知財活動に反映させる。これは知財を担当する者としての苦労であり、大きなやりがいでもあります。特にZOZOでは前例の無いものをゼロから考えたり、スピード感をもって進行する場面が多いため、知的財産部として携わったときの達成感はとても大きく感じます。
例えば、事業の現場ではたくさんのアイデアが生み出されますが、サービスに実装されるアイデアのすべてが特許になるわけではありません。逆に、サービスに実装しないアイデアが特許になることもあります。そうしたアイデアを特許にすべきかどうかは、コストや社内外への影響を考えながら判断をしています。
常に社内の動きにアンテナを張り、新たなアイデアが生まれたり、プロジェクトが立ち上がったりしたタイミングから担当者の思いを聞き続け、必要なタイミングが訪れれば知財として守る。これこそが私にとっての「知財責任者の自事」です。常に斬新なサービスや技術に触れ、日々新鮮な気持ちになれるZOZOは、その舞台としてうってつけだと感じています。
※本記事は、2025年4月3日の公開日時点に基づいた内容です。
コーポレート本部 / 2019年中途入社
森田 泰弘
メーカー企業やエンターテインメント企業での知財業務を経験後、2019年に株式会社ZOZOへ中途入社。現在は、特許、意匠、商標、著作権などのZOZOの知的財産に関する業務を担う知的財産部のディレクターを務める。趣味はウェブサイトや動画などで世界各地の景色や街並みを楽しむこと。
知的財産 特許は現在採用募集中です